少人数制ハンズオンスクール
定員5名 5時間 39,600(消費税込・1名あたり)他の参加者のスキャンも参考にできるので、1人では気付きにくいポイントやコツを学べるのもグループ実習の魅力です。
開催日程はこちら
1対1個別ハンズオンスクール
定員1名 2.5時間 59,950(消費税込・1名あたり)集中的に時間をかけて学習したい方におすすめ。掲載コースの中からご希望のコースを選択してご受講いただきます。
開催日程はこちら
スクール内容のご案内
本スクールは、これから末梢動脈エコーを始める方、始めたばかりの方を対象とする主に描出法を学ぶ初級コースです。
腎動脈エコー検査の意義や臨床での生かし方を確認し、腎の解剖の確認と腎動脈の描出方法および血流計測のコツを学んでいただきます。
また、下肢動脈エコーは閉塞性動脈硬化症(peripheral arterial disease : PAD)の診断に有用な検査です。4点(総大腿・膝窩・後脛骨・前頸骨動脈)描出法や腸骨動脈、膝窩動脈の観察ポイントとともに血流評価についても解説します。
※ 講師は現役で医療機関に勤務するベテラン超音波検査士です。
※ 被験者モデルは健常者です。
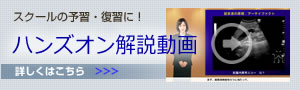
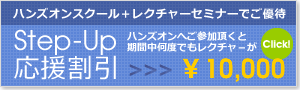
プログラム
1腎動脈エコーの意義及び描出法
なぜ腎動脈エコーをするのか、それを臨床でどう活かすのか、腎動脈エコー検査の意義をレビューします。
2腎動脈起始部描出法
腎動脈起始部の解剖や血管描出、血流速度の計測を行ないます。
3腎実質、側腹部よりアプローチ
腎実質の径、実質血流の計測、側腹部よりアプローチを行います。
4下肢動脈エコーの意義及び描出法
治療に直結した下肢動脈エコー法、検査の意義をレビューします。
54点(総大腿・膝窩・後脛骨・前頸骨動脈)描出、各部位のパルスドプラ測定
4点(総大腿・膝窩・後脛骨・前頸骨動脈)描出法および波形の評価を行います。
6腸骨動脈、膝下の動脈アプローチ
腸骨動脈の観察ポイントとコツ、膝下動脈の観察を行います。
※スクール当日はできるだけ多くの実技時間をとるため、テキスト解説の講義は要点のみとなる場合がございます。
※上記プログラムは、当日の進行状況によって変更になる場合もありますのでご了承ください。





